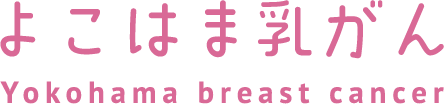乳がん治療終了後に妊娠の可能性を残すために、治療前に受精卵凍結、卵子凍結、卵巣組織凍結などを行い、妊孕性を温存することが可能です。希望される場合は、妊孕性の温存を行っている施設と連携しながら乳がん治療を行っていきます。 受精卵凍結とは採取した卵子とパートナーの精子を受精させ、凍結し保存しておく方法です。本方法は不妊治療として行われる体外受精の手法として広く実施されており、有効性・安全性が確立された技術です。パートナーがいらっしゃる方には、この方法が第一選択となります。患者さんの年齢により大きく異なりますが、凍結胚1個あたりの妊娠率は約20~30%と言われています。
卵子凍結は、患者さんから採取した卵子を受精させずに凍結しておく方法です。患者さんの年齢により大きく異なりますが、卵子1個あたりの妊娠率は 4.5~12%程度とされています。治療を受けられる時点でパートナーがいない方が対象になります。 卵巣組織凍結は、臨床試験段階の治療と位置付けられています。腹腔鏡手術により卵巣を摘出して、卵子が多く含まれる卵巣組織の一部を凍結保存しておく方法です。